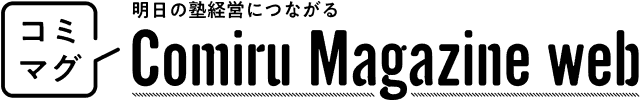| この番組は「教える」をなめらかにし、みんなの「かわる」に寄り添うを掲げるPOPER代表の栗原慎吾と、山村で自宅を図書館として開き、「地に足をつける」生き方を探求する思想家・社会福祉士の青木真兵が、さまざまな「教える現場」を訪ね、その奥深い呼吸に耳をすませながら、教育の本質を問い続けるトーク番組です。=構成・向山夏奈 |
|
土屋明(つちや・めい)さんプロフィール 1993年、東京都青梅市生まれ。同志社大学文学部哲学科卒業。2020年から神奈川県相模原市の自立援助ホーム「緑のまきば」で働き、青年の自立支援に携わっている。娘の小学校入学をきっかけに、相模原市北西部の里山・藤野へ移住。夫と子ども二人、猫二匹とともに、自然に囲まれた暮らしを楽しんでいる。読書と昼寝、そして夫の作るご飯をこよなく愛する。保育士資格を有し、相模原市の養育里親としても活動中。NPO法人ベテルスは、神奈川県相模原市に根差し、「繫がる」を合言葉に、虐待や貧困といった課題に取り組んでいます。主要事業である自立援助ホームでは、住まいを必要とする青年に、仕事や学校に通いながら安心して生活できる居場所を提供し、自立に向けた支援を行っています。 |
自己責任社会の「ひずみ」を修復する仕事

栗原 前回は、明さんが働いている「自立援助ホーム」とはどんな場所なのかをお話ししてもらいました。親の事情でホームにやってきた子たちが、自分基準の人生をみつけるために、まずは「ふつうの生活」が必要だというお話がありましたね。
その一方で、家に帰って休めるというか、もっと広い意味で一人ひとりが落ち着ける「居場所」みたいなものが、この社会全体で減ってきていると思いませんか。
土屋 たしかに、家庭以外の居場所や、支えてくれる地域の人が大事ですが、今は本当に少ないですね。居場所は子どもだけじゃなくって、親にも必要です。
私もこの仕事をするまでは、虐待をする親のことをどこか特殊な存在だと捉えていたんですよね。「虐待をする親=ひどい親」、みたいな。でも、自分も虐待をする親と紙一重なんだなって。すごくつらくて、自分の子どもを怒鳴ったことも、手をあげそうになったこともある。本当に誰にも起こりうること。
そういうときに、その親御さんが助けを求められる存在がまわりにいて、そして、支えを受けられれば、きっとなんとか乗り越えられる。私たちのところにくる女の子たちの親御さんは、おそらくそういう居場所や支え手が足りなかったんです。
あるいは、「虐待の世代間連鎖」と言われるように、親御さんが同じような経験をしていたケースも少なくありません。自分がされてきたことを子どもにもやってしまう。それで傷ついた子たちが私たちのところにやってくるという構図になってしまっている。私たちはそれを止めたいっていうか、この子たちには癒しの過程をたどってほしいと思っています。
その一方で、親御さんたちにも居場所や癒しの過程があったらどれだけよかっただろうかって思わずにいられない。環境が違えば、きっとまた違った子育てができていたんじゃないかって。だから、虐待の問題は、その家庭だけの問題じゃなくて、社会全体の問題として捉えるべきなんですよね。
「社会的養護」の理念は「社会全体で育てる」ことだと最初にお話ししましたけど、児童養護をしている人たちの狭い世界だけじゃなくて、本当にぜんぶの人がこの問題を知らなければいけない。困っている家族がいる、貧困や孤立と戦いながら生き延びている人がいる。テレビの中の話じゃなくて、隣の家で起きていることなんだと知ってほしいって思います。
栗原 抽象的な社会だけではなくて、地域でのつながりも大事ですよね。たとえば、同じクラスの親御さんに助けてもらうとか。社会的養護の第一歩は、一人ひとりの人間がちゃんと「いい感じ」につながっていくみたいなことかもしれない。いまはあまりにも家庭の中に閉じすぎて、社会全体が分断されてしまっているから。
青木 競争社会の結果として孤立してしまっている。ぼくたちの親世代は経済成長を経験して、「いい学校を出て、いい会社に入れば幸せになれる」っていう、今の自己実現・自己責任の社会の前提を作ってきた世代です。
社会を物質的に豊かにしたし、絶対的な貧困によって死んでしまう人たちを救ったという面があった一方で、競争によって一人ひとりがバラバラになり隣近所のつきあいがどんどんなくなっていって、地域社会の分断を生んだ時代でもあった。そのツケが今いろんなところにまわってきているんだと思っています。
子どもの一生が親の都合で決まってしまい、それなのに自己責任と言われる。そして親も子も地域の中で孤立している。明さんがやっていることは、それをちょっとずつ修復していくっていうことなのかな。
社会をリペアする仕事の価値が軽視されている
栗原 でも、メディアには競争社会を「勝ち抜いた」人ばかり出てきて、リペアをしている人たちに目がいかないじゃないですか。
青木 そう。しかも、そういう人たちのほうが労働に対する対価が高いわけで。
栗原 本当の意味で社会を支えているのは現場の人たちなのにね。リペアをする人たちの仕事の価値を正当に評価できる人が、まっとうな判断をしてほしい。
土屋 いま人材の確保が本当に大変で……。私たちの施設もそうですし、児童養護とか、社会福祉全体で見ても本っ当に人が足りていないんですよね。私たちみんなが、その善悪は別として資本主義社会の恩恵を受けているからこそ、そこから生まれたひずみにはみんなが関わらなきゃいけないって思うんですよね。
それなのに、施設ができるときに地域社会で反対運動が起きたりする。障害者手帳をもっていると、不動産屋さんに断られたりもする。契約するにも保証人をみつけにくいというハードルもあります。社会的養護にいた子が就職時に差別されることも、いまだにあります。一つ一つのことに対応することも大事ですし、その問題が起きている構造の部分にも働きかけていかないといけません。
生き生きとしたコミュニティが社会の処方箋になる
栗原 「もう資本主義って限界ですよね!」みたいな言説ってけっこうあるじゃないですか。でも、ただそれを言うことと、実際にその外側を実感してみて初めて腑に落ちるのとはぜんぜん違うと思うんです。
ぼくは昨年(2024年)の4月に藤野に引っ越してきて、古き良き日本のコミュニティを初めて経験したんですよ。資本主義的な世界のど真ん中にいたら「なんでこんなことしなきゃいけないんだ……」っていうようなこともあったんだけど、やってみて初めて「なるほど」ってわかったんです。そういう実感を持った人たちが増えていかないかぎり、資本主義は駆動し続けていくような気がします。だから、みんな、田舎にいったほうがいいんじゃないかな……(笑)。
土屋 それは私も本気で思います! 藤野ってほんとうにいいところ。私たちが子どもだったころの田舎というか、地域社会がいきいきと生きている。子どもが駆けずり回っていて、それを近所のおじさんたちが見てくれていて、たまに注意してくれる。お隣さんと顔が知れた関係が藤野にはあるんですよ。
もちろん藤野にもいろいろ課題はありますが、人と人のあったかいつながりがまだある。そして、そういうつながりを必要としている家庭や子どもはいっぱいいる。
栗原 単純に生活コストとか土地の安さを理由にするんじゃなくて、コミュニティが息づいている田舎の価値が広まっていくことが、社会に対する現実的な処方箋になると思っています。
青木 ぼくは体調を崩して9年前に東吉野村に移住したんだけど。町の何がしんどかったかって、学習塾ですよね。駅の周辺に塾がたくさんあって、横断幕?に「東大合格●人!」って書いてあるじゃないですか。あれが発するメッセージにやられちゃったんですよね。
学歴! 偏差値! テストの点数!を掲げて、人間のすべてが数値にできるんだっていうメッセージを受けてしまって、しんどかった。まあ、コミマグは塾の経営者が聞いてくださってるから、かなり微妙な発言なんだけど(笑)。 二人はどうして藤野に引っ越したんですか。
土屋 私は直感です! 藤野という土地と、子どもがいま通っている学校のことを知ったときに「ここだ!」って思ったんですよね。「私が住みたかった場所ってここだ」って。だから、理由を言ってもその直感を補足するような「後付け」になっちゃうんですよね。藤野は自分自身が育った青梅市に近いものがまだある場所だって思ったし、私が教育において大切にしていることがある学校でした。
栗原 ぼくはそういう直感ではなくって、むしろ1年くらい住んで、やっとなじんできたっていう感じです。藤野でいろんな体験をするなかで、これまで頭の中で考えてきたことがやっと腑に落ちたっていうか。自分を実験台にしながら、人と人とのつながりとか、あいさつとか、そういったものが人間の相当深いところで根本として必要とされているんじゃないかなってことに気づいていったんです。自分の成育歴の中に、そういうものが一切なくても、その大事さがわかった。
「ただそこにいていい」という居場所を

青木 そういえば、あなた、ボーイスカウトやってたでしょう?(*編集部註:青木氏と栗原氏は従弟であり、幼少期を共に過ごしてきた)
栗原 そうなんだけど(笑)。それこそ、今はあのボーイスカウトの団長をやっていたおじさんたちの気持ちがわかるんですよ。それまでは、「休息する日になぜさらに疲れることをしなくちゃいけないんだ」って思ってた(笑)。
青木 経済合理性で考えると、土日にボーイスカウトの活動をして汗をかくことは「疲れること」「無駄なこと」なわけですよね。つまり「コスパ」が悪いってことじゃない。そこの尺度では測れないものが、人間には必要ってことだよね。
栗原 そうそう。競争社会とか、経済合理性とか、ぼくはそういうものの「外側」に行きたいわけですよ。本当はそういう広い地平があるのに、多くのビジネスマンが無視して生きてしまっているから。
青木 でも、ぼくはボーイスカウトは大嫌い。
栗原 だからぼくより先に都心に限界がきたんだね(笑)。
青木 そう、ぼくは究極の合理主義者なんで。合理主義を突き詰めた結果、「これ以上、街で生きるのは限界だ!」って。それで引っ越した。でも、田舎に来たらまったく合理性がなくて。寄合でもずっと駄弁っているだけ。地元の方から「ぜんぜん顔出しに来ないじゃないか!」なんてことも言われて。「顔を出すことって意味あんの?」って驚きました。
でもそこで初めて、顔を出す(存在をその場に置く)ということは、社会的に有意義なことをする次元にはなくて、そこにいるだけでいい、というか、「いること」そのものに意味があるんだっていうことを知りましたね。
土屋 あ〜、逆に私はそういう目的のない集まりが大好きなんですよ。ホームの施設長が、「そこにいるだけでいいんだよ」って、よく言っています。あなたが生まれてきて、ここに来てくれただけでいいんだって、そういうメッセージ。それは本当にもう、私たちが大事にしていることです。
青木 かつてのコミュニティにあった「ただそこにいていい」を明さんの施設が代わりに補ってるのかもしれませんね。近代社会の中では一人ひとりがバラバラになっちゃうから、人間が人間らしく暮らすために、いろんなアプローチによって補強しているっていう感じなのかなって。 そろそろお時間ですが、今日はいかがでしたか。
土屋 すごい緊張しました~(笑)。自立援助ホームってマイナーな存在なので、テーマに取り上げていただいたのはすごくうれしいですし、今日お話ししたことを持ち帰って、また自分の働きの中で考え直したり、見つめ直したりしたいと思います。いいきっかけをいただきました。
青木 そんな言葉をいただくと、なんだか役に立ってる気がしちゃいますね。ぼくはふだん、できるだけ役に立たないことをしようと思ってるんですけど(笑)。
土屋 役に立たせてしまって申し訳ないです(笑)!