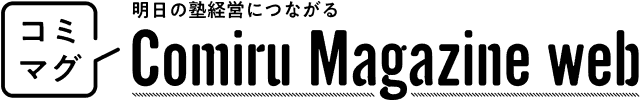| この番組は「教える」をなめらかにし、みんなの「かわる」に寄り添うを掲げるPOPER代表の栗原慎吾と、山村で自宅を図書館として開き、「地に足をつける」生き方を探求する思想家・社会福祉士の青木真兵が、さまざまな「教える現場」を訪ね、その奥深い呼吸に耳をすませながら、教育の本質を問い続けるトーク番組です。=構成・向山夏奈 |
青木 今日は神奈川県相模原市藤野にやってまいりました。栗原さん、いかがでしょうか。
栗原 あんまり本調子じゃないですね。花粉症が始まりました。
青木 何花粉ですか?
栗原 スギ花粉です。
青木 はい。ということで(笑)、今日は2回目です。初回で打ち切りにならなくてよかった~! 今日のゲストは福祉分野の方ですね。
栗原 ぼくのリクエストです。POPERのお客さんたちは「塾や習いごとを通じて人間を育てていきたい」という想いをよく語ってくれるんですけど、あくまでちゃんとサービスを売って、自分でお金を稼いで、という経済原理の中にいる方たち。でも、福祉は経済原理の外側にある営みですよね。人と人とが関わることを純度高くやっているのが福祉だとぼくは思っているんです。
|
土屋明(つちや・めい)さんプロフィール 1993年、東京都青梅市生まれ。同志社大学文学部哲学科卒業。2020年から神奈川県相模原市の自立援助ホーム「緑のまきば」で働き、青年の自立支援に携わっている。娘の小学校入学をきっかけに、相模原市北西部の里山・藤野へ移住。夫と子ども二人、猫二匹とともに、自然に囲まれた暮らしを楽しんでいる。読書と昼寝、そして夫の作るご飯をこよなく愛する。保育士資格を有し、相模原市の養育里親としても活動中。NPO法人ベテルスは、神奈川県相模原市に根差し、「繫がる」を合言葉に、虐待や貧困といった課題に取り組んでいます。主要事業である自立援助ホームでは、住まいを必要とする青年に、仕事や学校に通いながら安心して生活できる居場所を提供し、自立に向けた支援を行っています。 |
「自立」とは自分の人生を生きていくこと

青木 「自立援助ホーム」ってあんまり聞かないですよね。
土屋 そうかもしれませんね。まず仕組みのことから説明すると、家庭で暮らすことが難しい子を社会全体で育てていくための仕組みを「社会的養護」といいます。みなさんが耳にすることが多いのは児童養護施設や里親だと思いますが、自立援助ホームも「社会的養護」の一つです。
義務教育を終えて、児童養護施設などを退所した15歳〜20歳くらいまでの子どもたちが対象です。「自立」に向けて、ホームから学校に通ったり、仕事に行ったり、一人暮らしするためのお金を貯めたり、そのために一定期間いる場所ですね。
青木 明さんが働いている「緑のまきば」の定員は?
土屋 女の子のためのホームで、定員は6名です。年齢層は16歳〜22歳とわりと幅広いですね。もともと自立援助ホームは「働いている子たちが生活する場所」という役割が強かったんですが、今は学校に通っている子が多いです。夜間高校や通信制高校だけではなくて、普通高校に行っている子が増えてきていますね。
青木 どんな事情を抱えた子どもたちが多いですか?
土屋 家庭で不適切な養育を受けてきた子たちがほとんどです。あるいは、親が育てたかったけど、金銭的・健康的な事情によって、子育てを続けることが厳しかったケース。親は一生懸命育てているつもりなんだけど、ボタンの掛け違いが生じてしまって、子どもとの間にミゾがどんどん広がって、このままではお互いにダメになってしまうから離れて暮らしましょう、という判断に至った子もいます。
栗原 その子たちに対して、明さんが大事にしていることはありますか?
土屋 そうですね……、自立援助ホームの制度の目的には「(子どもの)社会的自立の促進に寄与する」と書いてあります。でも、そもそも「自立」ってなんだろう?って思いませんか。いわゆる経済的な自立をイメージされるかもしれませんが、私は「自分の人生を生きていくこと」が自立だと思っているんですよね。
というのも、うちのホームの子たちは、家庭の事情や貧困といった、自分にはどうすることもできない「周囲の都合」に振り回された結果、ここにたどり着いています。そういう子たちにとっては、自分で自分の人生を選び取って生きていくことがとても難しい。
本来、子どもたち一人ひとりには、やりたいことを実現していく力がある。だけど、私たちのところに来る子は、環境の影響でそれを一時的に奪われてしまっている。だから、私たちは何かを「教える」のでも「指導する」のでもなく、その子が持っている本来の力を取り戻すためのお手伝いを隣でしている、そんなイメージです。
青木 力を発揮できていないのは、本人の能力の問題ではなくて、そうさせている社会や環境があるということですよね。障害の分野ではよく「個人モデル」(できないことがあるのは心身に障害があるせい)から「社会モデル」(社会が大多数に合わせてつくられているから障害者にとって不利なことがある)へと言われています。
土屋 まさに「社会モデル」の考え方が必要だなって思います。たとえば、「どういうふうに生きていきたいの?」と聞かれても、「やりたいことがわからない」と答える子が多い。その子は、本来「やりたいこと」に割くためのエネルギーを、生きていくために使わないといけない環境に置かれてきたんですよね。「生きていくのでせいいっぱいだよ!」「死にたいってずっと思っている」という子もいます。その子たちにとって、生きることはどれだけエネルギーを使うことか、と思います。
だから、まずは「やりたいこと」を見つけられるくらいまで回復することが必要なんです。ここに来るまでに、とてつもなく困難な状況を生き延びてきた子たちにとって、安心して生活できる居場所であること。そんなホームでの日々の積み重ねが、子どもたちの力に繋がるのではないかと思います。
かといって、何か特別な関わりをしているわけではなくって……ただの「ふつうの生活」をしています。テレビや動画を見て「なにこれー!」ってげらげら笑い合ったり、一緒にご飯を食べたり。私たちはそういうことを通して、子どもたちの回復の過程に携わっています。
「当たり前」を押し付けてもうまくいかない

土屋 「当たり前の生活」を保障することも自立援助ホームが大切にしていることの一つです。親がつくったご飯を食べることや、家族と一緒に生活することをしてこなかった子もいますし、親の顔を見たことがない、という子もいますから。
でも、その「当たり前」がとても難しい。私たちが思っている当たり前って、他者にとってはぜんぜん当たり前じゃないから。たとえば、(水を飲む)グラスにご飯をよそって、それをお茶碗の代わりにしている子もいたりして。その子は「別に。フツーじゃん」って。たしかに、グラスで食べてもおかしくない。ただ私が育ってきた環境ではお茶碗が当たり前だっただけで……。
青木 たしかに、家庭って個人にとって最初の社会ですよね。そして、何が当たり前なのかがわからなくなってきているのが今の社会です。「いい大学を出て、いい会社に入れば安泰だ」みたいな価値観も薄れてきているし。そういうなかで「当たり前の生活」とは何か、向き合っていくのはなかなか難しいと思います。
土屋 そうなんですよ。「みんなで一緒に食事をとることを大事にしましょう」とか言っても、その子の心に響かない、ということがたくさんあって。そういうとき、私たちの「当たり前」は、その子たちがほしい「当たり前」でもなんでもない、ただの押し付けなんだって思い知らされます。
まわりの大人が勝手に「あなたにはこれが必要だよ」と理想像みたいなものを押し付けても、なんにもうまくいかないんです。そうやって、その子を「変えること」では変わっていかないっていうか。だって、それじゃあ今までその子のまわりにいた大人がやってきたことと、なんにも変わんないんですよね。
だから、その子が自分自身で「こうなりたい」って思えるものを見つけて、自分で状況を変えようとしないと、意味がない。私たちの支援は、そうやって自ら変わろうとするまでの過程に寄り添ったり、自分で変わろうという気持ちになったときに手助けする、みたいなことだと思っています。
栗原 一人ひとりが自分にとっての「当たり前」を手に入れていくことが、自立なのかもしれないですね。
土屋 「当たり前」を獲得していくなかで、自立していくのかもしれませんね。たとえば、高学歴の親をもって、その期待に応えようとしてずっと苦しんで、耐えて耐えて生きてきて、ようやく私たちに助けを求めてくれて、今ここで暮らしている、という子もいます。
その子はやっと、まわりの基準じゃなくて、自分の基準の人生でやっていける地点に立つことができたんですよね。そういう自分基準の人生をみつけるための場所でありたいなって思うんです。
栗原 家庭って、子どもにとって「最初の社会」であると同時に、外で傷ついたり、疲れた心を回復させる場所でもありますよね。そこでだけは甘えられて、パワーを回復させて、また外に出ていく。傷つかずに生きていくことは誰もできないから、「大変だったね」って話を聞いてくれる場所がないといけない。
きっと、明さんたちが「いってきます」「おかえり」「いってらっしゃい」、みんなでご飯を食べよう、ということを繰り返すなかで、子どもたちも少しずつ自分で立てるようになって、自分を獲得していくんだと思います。
土屋 そうそう。「当たり前」って難しいんですけど、私もそれでもやっぱり、「ありがとう」とか「ごめんなさい」とか、「おかえり」「ただいま」っていうやりとりがあるような「ふつうの生活」が人間の大事な部分を築いていくんだと思っていますし、この子たちとつくり上げていきたいと思っています。
――後編に続きます