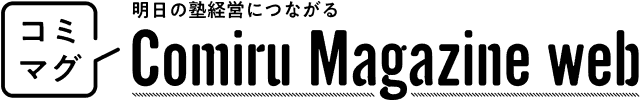| この番組は「教える」をなめらかにし、みんなの「かわる」に寄り添うを掲げるPOPER代表の栗原慎吾と、山村で自宅を図書館として開き、「地に足をつける」生き方を探求する思想家・社会福祉士の青木真兵が、さまざまな「教える現場」を訪ね、その奥深い呼吸に耳をすませながら、教育の本質を問い続けるトーク番組です。 |
|
高濱正伸(たかはま・まさのぶ)さん・プロフィール 1959年熊本県人吉市生まれ。県立熊本高校卒業。東京大学農学部卒、同大学院農学系研究科修士課程修了。1993年、「メシが食える大人に育てる」という理念のもと、学習塾「花まる学習会」を設立。『伸び続ける子が育つお母さんの習慣』、『小3までに育てたい算数脳』など、著作多数。 |
「モテる」大人になれ!
青木 今日のゲストは、花まる学習会代表の高濱正伸さんです。
高濱さんが理想とする「メシが食える大人になる」についてお聞きしたいのですが、「稼げる大人」ではなく、「メシが食える」なのが絶妙ですよね。
高濱 本来は「仕事をして生計を立てる」という意味ですが、ぼくからすれば仕事は嫌々やってちゃだめ。ぼくは「モテる」ってよく言うんですけど、男女関係なく好かれて、人から信頼されることで「人生楽しい!」って感じてほしい。だから、メシが食えるとは、自立して魅力的であるということなんです。
それまでは、入試に合格させるための塾しかありませんでした。でもぼくは、どの子も自分なりの力で楽しく生きてくのが一番大事だと思う。だから、そこをサポートする塾をつくりました。
青木 どんなことを子どもたちに伝えているのでしょう。
高濱 自分を見失わずに、「これが好きなんだ!」と言いきれるかどうか。その一点だと思います。そのために、小さいころは遊びまくる。自分が感じたことを日記に書く。かっこつけたり、褒められたりするために書くんじゃなくて、「本当の自分」を書くんです。ぼくは中3まで生徒会長で優等生を演じてたんですけど、日記にだけは「俺は本当はそうじゃない」って書いていました。そこだけは自分を偽らない。ネガティブな気持ちもきちんと書く。
自分を見失わず、好きを貫くために
青木 日記を書くことにどんな役割があるのでしょう?
高濱 自分の心を正しく見ることができます。自分の心を正しく見ると、人から与えられたことを鵜呑みにするのではなく、自分で考える力の基ができるんです。すごく簡単なのに、意外とみんなできていない。
「自分が何が好きかわからない」っていう大人がたくさんいますが、そんなはずないです。好きなものがあるのに、価値がないと思い込んでいるだけです。
原因の一つに、点数で競わされて、「自分はこれくらいのランクだ」って思い込まされる仕組みがあります。自分の外に評価基準があって、いい点数をとる、いい場所にいく、ランキングの上のほうにいくことばっかりやらされるでしょう。大人になっても「いい会社ランキング」があって、どこの会社にいって、給料をいくらもらうかで価値を決められてしまう。その大枠に囚われてしまうことで、自分を見失ってしまうんです。
青木 評価軸が自分の内側ではなく、外側にあるんですよね。それをぼくは「商品化」と呼んでいます。他者にとって必要かどうかで価値が決まると思ってしまっている状況です。
高濱 そうやって、商品価格で自分の中の価値を決めてしまうんですよね。自分が何をやりたいかが一番大事なのに、「それをやっていくらになるんですか?」と考えてしまう。
それはつまり、自分がない状態だと思うんです。「誰がなんと言おうと、俺はこれをやっているときが幸せだ」と言いきれない。否定したいのではなく、その手の罠がこの世に多すぎることが問題です。「テスト勉強して!」とか、「そんなことしてるのあなただけ!」とかってすぐ言われますから。
自分を見失わないで、何かが好きと言いきれるか。これが哲学につながっていきます。好きなものなんて、なんでもいいんですよ。落合陽一氏は子どものときからゴキブリの飼育をしていたそうです。親が「もうやめたら」と言っても、本人は一向に譲らなかったと。
哲学を持つために「日記を書く」
青木 自分なりの哲学を持つことについてもお聞きしたいんですが、いまは、「これをすればOK」という正解がない社会になっていて、哲学が持ちづらい世の中になっていますよね。
高濱 まず自分の心を丁寧にモニターすることです。日記の何がいいかというと、自分のわくわくするものがわかるようになっていくこと。たとえば、「すごく良い!」と話題の映画が自分にはピンとこなかったとき。それもちゃんと書くんです。心が震えたもの、夢中になって時間を忘れたものがなんだったかを書く。そうすると、自分のことがわかるし、楽しい時間が定着していく。そうやって言葉にしていくことです。
青木 自分の琴線にふれるものが何かを探るんですね。
高濱 正解がないなかでどう生きるか、何がいいと思うか。それが哲学ですから。ぼくは親が開業医で、医者になるのが一番いいとされていたんです。でも日記を続けていたことで、「子どもたちと遊んでいるときが絶対楽しい!」って言いきることができました。そして、この年齢までずっと楽しくいられた。この積み重ねのおかげです。
花まる学習会は「稼げたNPO」
栗原 成績を上げる、いい大学に入る!ではなくて、子どもたちが自分らしく生きていくためのサポート。高濱先生のアプローチって、ちょっと福祉的なところがありますよね。障害のある人たちがバリアのある社会で、どう自分らしく生きていくかの支援と似ているなと。
高濱 能力や成績ではなく、その子の目が輝いているかどうかが人生の価値だと思っていますから。ぼくの息子は障害があるんですけど、彼は風が吹いただけで、幸せそうにするんですよ。笑っているのを見ると、今日はいい日だったねって心から思わせてくれる。彼からどれだけ学んだかわかりません。
青木 障害のある人といると、魂の部分で共鳴するというか、ケアされる、癒されるみたいな感覚がありますよね。
高濱 わかります。「かわいそうな人にやってあげてる」じゃなくて、むしろこっちが救われてるんですよね。息子のケアに入っているヘルパーさんたちも幸せそうです。純粋にその子に触れていることの良さを知っているというか。
栗原 高濱先生は、「パートナー力」っていう言葉も使われていますよね。ぼくの解釈だと、存在そのものを認めてもらえる喜びがあって、その喜びによって相手も救われる、そしてお互いが変化していく、ということなのかなと。
まさに、花まる学習会では、子どもたちはそこに行けば認めてもらえるし、子どもが喜んでいることによって先生たちも喜んでいる。いいサイクルですし、それが商売として成り立っているのはすごいことだと思います。
高濱 人間として生きる喜びを見失わないために、商売として成立させることを考えるのがわりと得意なんだと思います。とりあえず株式会社の形を選んだだけであって、実際はNPOに近い。でも、いいことだけしても稼げないと続かない。社員の給料も上げていかないといけない。ぼくは自分の事業を「稼げたNPO」だと思ってるんです。きれいなことだけやるのが人生ではないし、お金をバカにしちゃいけない。両方やれるようになるのが、大人になることかもしれないですね。
自分の哲学をもって楽しく生きるのが教育
青木 高濱先生って、遊び場みたいというか、「はらっぱ」みたいな存在ですよね。でも今は大人が楽しく生きること自体が難しそうだと思います。
高濱 楽しく生きてる大人がまわりにいないのって、悲劇ですよね。アメリカの研究では、教育にとって一番大事なのは、どこに住んでいるか、だそうです。その意味するところは、どれくらい魅力的な大人がまわりにいたか。ぼくに言わせてみれば、哲学のある大人がたくさんいるところで育つことが大事。無哲学の問題は、あらゆる階層のあらゆる大人に突きつけられてると思います。流されている大人ばかりの中で育つと、子どもが世の中を信じられなくなりますから。
青木 ぼくは障害のある人たちのほうがよっぽど人間らしいと思っているんです。合理化しすぎた社会にコミットできない人のほうが、ある意味まともというか。そういう「ままならなさ」を持った人とパートナーを組むということも、楽しく生きるうえでは大事な気がします。
高濱 いまペットを飼うのがすごい流行ってるじゃないですか。あれは人間が生き物らしさを取り戻すためだと思うんですよね。生き物がありのままであることに、安らぎを覚えているわけでしょう。
青木 そうやって自然と手を切れないのが人間ですよね。ぼくは、たとえば精神疾患の人は医学的にどうこうというよりも、「自然の部分を多く持っている人」だと思う。そういう人たちと手を切って、合理化していった社会がいちばんスムーズかといえば違うだろ、と。それなのに、いまはトラブルをどんどんなくしていく方向にいきますよね。
高濱 いろいろ起こるからおもしろいのにね。道を間違えたら、「なんか面白くなってきたねー!」って面白がったほうがいい。トラブルを楽しいって思えるようになると、人生なんにも問題なくなる。「無駄な時間」なんて思わないほうがいいですよ。
栗原 高濱先生のやっていることは本当にシンプルですよね。だけど、みんな難しいことを考えちゃって、徹底できる人が少ない。そこで花まる学習会のメソッドを続けていくと、哲学をもった子になれるっていうことがポイントですよね。
高濱 優秀な子にうちの塾に来てほしいわけじゃないんですよ。どんな子が来ても、自分の道や哲学を持って楽しく生きていくことができれば、それが教育だと思っています。どんな子でも自立に向かっていけますよ、ということを大事にしています。
栗原 今日はありがとうございました。