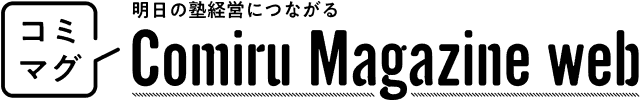| この番組は「教える」をなめらかにし、みんなの「かわる」に寄り添うを掲げるPOPER代表の栗原慎吾と、山村で自宅を図書館として開き、「地に足をつける」生き方を探求する思想家・社会福祉士の青木真兵が、さまざまな「教える現場」を訪ね、その奥深い呼吸に耳をすませながら、教育の本質を問い続けるトーク番組です。 |
|
向山夏奈(むこうやま・かな)さんプロフィール 1993年東京生まれ。独立系編集者。現代書館で雑誌『季刊福祉労働』ほか、障害福祉・ソーシャルワークの書籍を担当。2024年に退職し、パートナーで映像作家の宍戸大裕と映像・出版レーベル「くまのあくび舎」を始める。資本主義・能力主義を脱し、すべてのひと・いきものがそのままで生きられる社会をめざし、制作をおこなっている。 |
学生時代の生きづらさを障害者運動に救われる
青木 今日のゲストは向山夏奈さんです。
向山 今日はよろしくお願いします。障害者運動や障害者解放、ソーシャルワークをテーマに本づくりをしてきた書籍編集者です。
青木 障害者運動って、どんなものでしょうか。ひと言で説明するのは難しいかもしれませんが。
向山 私がいま障害者運動と名指しているものは、ざっくり1970年代くらいから始まったものをルーツとします。
これを私は、障害のある人とない人とが一緒に生きることを諦めなかった人たちが続けてきたものだと捉えています。たとえば、障害のある子ってふつうの学校に通ってきませんよね。多くは特別支援学校や特別支援学級に行く。それは障害のある・なしで人を分けたうえで「良い教育を施す」という名目のもとに行われる排除であって、そのシステムは非常に強固です。しかもそういうものを進めている人たちって、一見すごく「良いこと」を言っているように聞こえる。「すべての子に教育を与えますよ」とか「手厚く支援しますよ」とか。それに対して、結果的に障害者が排除されているだけじゃないか、良かれと思っての差別じゃないか、と批判を投げかけ続けてきたのが障害者運動です。
だから、障害者差別というのは、何かができる/できないによるものではなくて、本来あたりまえに人との人との間に築けるはずの協同性を剥奪することなんですよね。入所施設も、出生前診断もそう。「そこにいていい人」を選別する発想に対して抗ってきた運動、とも言えるかもしれません。
青木 そもそもなんで障害者運動に関心を持ったのでしょう。
向山 学生時代に感じていた生きづらさがきっかけです。就職活動にすごく苦しみました。面接のたびに仮面をつけて、よく知らないおじさんから勝手に評価をされるこの仕組みっておかしくないか?って。そんな苦しかった20代に、たまたま障害者運動家の介助をすることになりました。そのなかで、「人と人が本当に出会うとは何か」を教えてもらった感じがしました。
栗原 障害者介助をするなかで「人と人が本当に出会う」というのは、どんな経験なんですか。
向山 「お互いに、相手にとって都合のいい存在にならない」ということかもしれません。
私が介助に入っていた女性は、鳥を飼っていたんですよ。日勤の介助者の仕事は、その鳥のお世話をするところから始まる。私は当初、「この人自身がお世話される対象なのに、なぜペットを飼っているのだろう……」と違和感を持ったんですよね。今思うとほんとにヤバい学生……。
で、あとで「いや、誰だってペットと暮らす楽しみを持っていいし、それを勝手にジャッジしてしまう私って何目線なんだろう?」ってとことん考えて。私は迷惑をかけられたくないだけ。相手に「都合のいい存在になってほしい」と願っているんだ、とハッと気づきました。自分自身の中にある暗闇を見つめる。そして、どうしたら目の前の人の「その人らしさ」を侵害しないようにできるのかを考える、その繰り返しだったように思います。
栗原 自分自身が明るみに出されるような経験ですよね。
向山 障害のある人を前にすると、自分が引きずり出される感じがあります。
もう一つ。親もとや施設を飛び出して地域でアパートに暮らしている(自立生活をしている)障害当事者って、みなさん「解放のエピソード」を持っているんですよ。たとえば、障害のある先輩が「おい、タバコ」と介助者に指示して火をつけてもらうのを見て、「いいなあ」って思った、とか。
私はそれを聞かせてもらうのがすごく好きなんです。自分自身を縛るものから解放した結果として、いま私の目の前で生きて語ってくれている。けれど、その人と相対している私は、果たして社会のしがらみから自由になっているのか? 自立生活をしている障害当事者と向き合うと、自分自身と社会との関係を意識せざるを得ない。そこに、個と個が出会えたと感じる瞬間があるのかなって。
障害者運動に「本づくり」で関わる
青木 今の向山さんの運動とのかかわり方って「本づくり」を通してがメインだと思いますけど、なかなか珍しいですよね。社会運動ってパワーが求められるけど、本って即効性があるわけでもないし。
向山 しかも儲からないですしね(笑)。
一つは、記録の重要性です。本のあるなしで歴史的な評価が左右されてしまうところがあって。運動でものすごく重要な役割を果たした人なのに、主著がないために後世に伝わらない、というケースがけっこうあります。
もう一つは、言葉が運動に果たしてきた役割が大きいと思っているからだと思います。差別に遭い、自己を奪われてきた人たちが、言葉を獲得していくなかで仲間をみつけ、運動に発展していくっていうことは多々ありますから。自分の仕事がそういうことに少しでも寄与できたら、という思いはあります。
……こういうと、すごく高尚な心がけみたいですけど、ここ数年の私にできたことがたまたま本づくりで、たまたま運動関係者にアクセスしやすいポジションにいたからやらせてもらってる、っていう感じです。
ビジネスの中でいかに人と人のつながりを作るか
向山 慎吾さんが連載初回で「ビジネスを通して人と向き合いたい」って言っていたことが希望だなと思いました。今は障害福祉の世界も消費者意識が強くなっていて、支援者と利用者という関係性から一歩踏み出すことが難しくなってきています。
だから、慎吾さんがやっていることって思い切りビジネスなのに、「人と向き合う」ってどういうこと?って。
栗原 利益を求める「数値化されたレイヤー」の中だけにいると、人間ってどんどん元気がなくなっていくんですよね。数値化された世界って、自分も数値として見られるし、相手を数値として見るし、あり方が決定されちゃってる。でも本来、人と人との付き合いっていうのはそうじゃない。ビジネスでも社員同士のつながりだったり、お客さんとも単なる取引だけではない人としてのつながりを求めていかないとしんどいです。
向山 でも、「本当のあなたと出会いたいんです!」と言っているだけではなかなかその目的を果たせないのが難しいですよね。「ビジネスとして成功する」というA面の目的がしっかりあるからこそ、B面での人との深いつながりが成立する気がします。人間って、何かを一緒にやる、とか、同じ方向にむかって動いていくときに、深いつながりができるんじゃないかなって。
栗原 人と人の間に触媒になるような何かがなければいけない。真兵がやっている合気道もそうだと思うんだけど、師匠と一緒に技術を身に着けていく過程のなかで、溢れてでてくる剰余みたいなものがあって、そこに人と人との交流が生まれるんでしょうね。
青木 向山さんのお仕事でもある本づくりにも近いものがあるんじゃないですか。
向山 考えてみればそうですね。著者と編集者のあいだで一冊の本を作り上げるという共通の目的に向かっていくなかで、著者の「本当の声」みたいなものが出てくる。それを無視せず、拾い上げながら、作品にしていく。それが編集の仕事だなって、さいきん思うようになりました。
青木 すごく稀有な仕事ですよね。経済生活のなかで「本当の声」を出しちゃったらめんどくさくなるから、「引っ込めといて!」ってするのが社会人。でも、本づくりにはそれが出ていないといい本にならないし、つまんない。そのめんどくさいところを怠らずにやっていくわけですよね。
向山 そう、スーパーめんどくさい仕事なんですよ(笑)。でも、ふつうに社会生活を送っていたら寸止めしてしまうような「本音」の中にこそ、読者の心を打つものが含まれていたりするんです。だからやっぱり、人間には数値化や役割を超えた深いつながりが必要なんですね。
何をコストと呼ぶのか
青木 前は会社に所属していて、今はフリーでやっていますよね。違いはありますか?
向山 あの……確定申告の話してもいいですか?(笑) 確定申告前までは、「自由でかっこいいことしているんだ!」と思ってたんですけど、確定申告したら、なんかがっかりしちゃって。税金を払うためにこんなにあくせくさせられて、けっきょく勤勉な納税者にさせられるんだ、なーんだって。解放されても納税が待ってました。
栗原 ぼくも会社をやめた年の国民健康保険料と住民税にはがっくりきましたね。「おれ、なんかやっちゃったかな?」っていうくらいの請求がくる(笑)。
青木 「お前は会社を辞めたからこうなったんだぞ」っていう、見せしめね。
向山 今の生活は楽しい。でも収益でいくとマイナスでは?みたいなこともあります。
青木 すべてをお金で考えてしまうと、いざ行動に移すときに「この人と会うとお金にならない、だからやめよう」みたいに制限をかけちゃいますよね。でも、それをやっちゃうとどんどんつまんなくなる。
栗原 ぼくはもう、「コスト」っていう言葉を使わないほうがいいんじゃないかって思ってます。
青木 数値化すると、人もモノも、作業も情報も、すべてが横一列で扱われるじゃない。そうなってくると、計算可能なものが重要視されて、質が問われなくなるんだよね。そこでまず人件費が削られるでしょう。ひと言でいうと、ぼくたちはその状況でいい仕事ができるのか、っていうことなんですよね。
向山 そこはやっぱり、命ベースで考えてほしいですよね。命ベースで考えたうえで、それから数値のことを考えてほしいなって。国民民主党の玉木雄一郎氏は「保険料を見直すために、終末期医療や高齢者医療を見直す」とか、予算を減らすために「尊厳死法の法制化が必要だ」とか言って票を伸ばしましたよね。でも、そこでコストと呼ばれるものを削ることで何が失われるのか、よく考えてほしい。譲り渡してはいけない命までも削ってしまっているのが今の日本なんですよね。人件費もそう。それに対して使うお金をコストと呼んでいいのだろうか?って。
「説明できないお金」が組織をいきいきさせる
栗原 コストや投資に分解されないようなお金、つまり「説明できないお金」も、企業にとっては大事だと思います。「自分たちがやりたいからここに何百万円いれました」みたいなことをやってる会社はいきいきしてますから。
向山 なるほど。中村哲さんがアフガニスタンでハンセン病の支援をやっていたときに、すべての患者さんにクリスマスケーキを自腹で買って配るっていうエピソードがあります。哲さんが、現地のワーカーさんに「このケーキで1週間は飯が食える。こんなぜいたく品はもったいない」って止められるんですよね。でも哲さんは「かまわん。これは俺の道楽だ。それくらいの贅沢は好きにさせろ」って一蹴するんですよ。ここがめっちゃ好きで。
栗原 説明できないお金があってはいけません!っていうことが100%になった瞬間に、機械みたいになっちゃうんですよ。自分も働いている人も、組織も機械になっちゃう。やりたいからやってる、でも誰かのためになる道楽みたいなものがないといけなくて。このラジオとかも道楽みたいなものですからね。だから、無くなったらだめですよ!