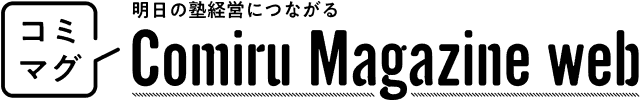| この番組は「教える」をなめらかにし、みんなの「かわる」に寄り添うを掲げるPOPER代表の栗原慎吾と、山村で自宅を図書館として開き、「地に足をつける」生き方を探求する思想家・社会福祉士の青木真兵が、さまざまな「教える現場」を訪ね、その奥深い呼吸に耳をすませながら、教育の本質を問い続けるトーク番組です。=構成・向山夏奈 |
|
中村真広(なかむら・まさひろ)さんのプロフィール 1984年千葉県生まれ。東京工業大学大学院建築学専攻修了。建築家の塚本由晴氏のもとで学ぶ。不動産デベロッパーの株式会社コスモスイニシア、ミュージアムデザイン事務所、環境系NPOを経て、2011年株式会社ツクルバを共同創業し、2019年東証グロース市場に上場。2023年10月に取締役を退任し、事業の一部をバ・アンド・コー株式会社として引き受ける。株式会社KOUを創業し、2019年より代表取締役。自律的に生きる人を増やすために、キャリアデザインプログラム「Willnext(ウィルネクスト)」を展開。同時に、藤野エリアにて、実験的集落「虫村」やカフェ兼イベントスペース「カドナリ」等を起点に、新しい経済モデル、コミュニティ、サスティナビリティなどをテーマにした地域アクションを展開。人口減少社会における新しい地域モデルを探求している。「場の力で人生を肯定できる世界をつくる」をミッションに掲げて、時代の兆しから新たな場をつくることがライフワーク。 |
金融資本主義は「終わりのないゲーム」
青木 中村さんは2023年に「ツクルバ」の共同代表を退任し、神奈川県相模原市藤野に移住。現在は、「虫村(バグソン)」の村長として集落をデザインするかたわら、山村で人と人をつなぐための不動産ビジネスも展開されています。ユニークな活動の背景にはどんな思想があるのでしょう。
中村 ぼくは今3つのレイヤーを行き来しながら生きていると考えています。
①スタートアップ(=金融資本主義)
②ローカルエコノミー(=金融資本主義ではあるけれど「ゆるい」経済活動。藤野での活動など)
③アートの領域(「虫村」での集落づくり=家賃を設定していない「商品のない世界」。数値化された世界からの解脱)
青木 ①と②はどちらも資本主義ですよね。二つの違いはなんでしょうか。
中村 経済の回転速度が違います。①金融資本主義では、株式市場で成果を上げる銘柄であり続けることが求められる。つまり、利益を出して株主にリターンを出すゲームの中に常にいる状態です。対して、②ローカルエコノミーはそこまできつくない。
青木 ローカルエコノミーは、お金だけの世界ではないということですか?
中村 どちらも資本主義の中の経済活動であることは同じですが、ローカルに行けば行くほど遠心の外側になるというか、回転速度がゆるやかですね。たとえば、ぼくが藤野で手がけるカフェ「カドナリ」も、融資に利子をつけて返済しないといけない。だけど、この場がきちんと存続すれば返せる金額です。
対して、ベンチャー企業はVC(ベンチャーキャピタル)から増資を受けて、株を切り売りして、10年スパンで時価総額を10倍にしないと!という、ハイリスク・ハイリターンな戦い。ローカルエコノミーとは「ゲームが違う」っていう感じですね。
栗原 ①の金融資本主義は、言ってしまえば「終わりのないゲーム」なんですよね。だから、経営者は会社の業績をあげることに躍起になり、突飛なことをアピールし続けなければならない。起業家をやっていると、「儲かるかどうか」を基準に考えるようになって、そのうちに自分を評価してくれるものが株価だけになってしまうんじゃないかと思うときがあります。
中村 わかります。「こんな変化を起こしたい!」という初期衝動でビジネスを始めたはずなのに、その先には金融資本主義しかなかったりして、「なんのために起業したんだっけ?」という葛藤に襲われることがあります。そこで悩んでいる人たちに、今日のぼくたちの話は響くかもしれませんね。
青木 ぼくはそういうすべてを数値化するような「都市の原理」と距離をとりたくて、東吉野村(奈良県)に引っ越したんです。
中村 しかも、都市部はすべてがサービス化されていますよね。お金を払えばどんなサービスでも受けられるけれど、「購入」と「消費」しか選択肢がなく、その範疇を超えられない不自由さがある。たとえば、ベランダにコンポストを置いてみても、「できた肥料を使える庭がない!」「じゃあお金を払って農園を借りようか」となってしまったり。自分の手で暮らしを作ることにコミットしにくい。そう気づいたときに、自分の手で暮らしを作れるような、余白がある場所で生活したいと思いました。それがぼくが藤野に移住した理由の一つです。
アートの領域としての「虫村(バクソン)」

青木 藤野では「虫村」という集落をつくっていますね。その際に描いたビジョンはどんなものですか。
中村 まずは子育てのことです。都心で核家族が子育てをするのって本当に「無理ゲー」で、どうにかしようと思ったらサービスを使うしかない。そこで、「虫村」では拡張家族のように複数の家族でお互いの子どもを見ながら、長屋のように暮らすことを考えました。
もう一つは、感謝経済のようなものを実現すること。ぼくらは自然からギフトを受けて生かされている存在なのに、そのことを忘れている。資本主義が行きつくところまで行きついて、ついに自分の時間や人生までをも数値化してお金に換算するようなことまで起きています。つまり、「商品化」という事象が人が生きていくうえでのボトルネック(制約)になってしまっているんじゃないかと。だから、虫村は商品のない場所にしてしまおう、と思ったんです。
3つ目に、オフグリットや再生自然エネルギーを使いながら、地球にやさしい建築様式による暮らし方を実践すること。この3つを掛け算してできたのが「虫村」です。
青木 冒頭にでてきた3つのレイヤーのうち、虫村は③アートの領域ということになりますね。
中村 アートのレイヤーは、直感や衝動を優先するレイヤーです。マーケットがそこにあろうがなかろうが、やらざるを得ない初期衝動でつくる。「衝動だけでやるものづくりって、超たのしー!」と思いながらやってます。
青木 ぼくも東吉野に移住してからは、直感で生きるしかないと思うようになりました。というのも、圧倒的な力を持つ自然のなかで生活を送っていると、細かく計画を立ててもしょうがないから。
栗原 ぼくも藤野に来てからそういう割り切りができるようになったかもしれないです。
青木 そもそも生きものは計画なんか立てないですからね! 藤野や東吉野村に住んでると、「いや、生きものって本来こうだから」って言いきれるようになるのかもしれない。
自律分散型システムがローカルを救う

青木 ここまで3つのレイヤーについてお話してもらいましたが、そもそも、どうしてこんなことを思いついたんでしょう。
中村 20代で右も左もわからずに起業したときは、金融資本主義の世界しかないんだと思ってました。でも、そうじゃない世界の存在に気づき、それぞれを楽しめるように生きていきたいと思うようになった。あと、その時々に直面している課題の内容によっては、3つのレイヤーを分けたうえで取り組んだほうがいいこともあるのかもと。「混ぜるな危険」というか。
青木 「混ぜるな危険」?
中村 たとえば、街づくりは金融資本主義だけで考えないほうがいい、とかね。ぼくのパパ友が写真館兼エステサロンを開業しました。その物件は、虫村ができる前にぼくが仮住まいにしていた家でした。パパ友からその構想を聞いて、ちょうど物件が空いているから一緒にやりましょう、と。でも、同じことを東京の不動産ビジネスで考えると、リノベーションして、家賃いくらで、利回り何%で、投資回収いくら、ということを追求しなければいけない。そうなると、家賃のリスクで商売が成り立たず、つぶれてしまう。つまり、東京のやり方を地方に当てはめると、面白いコンテンツが生き延びないんです。でもぼくは有意義な場所になると思ったので、「オーナーとして一緒にリスクテイクしていきましょう」と、歩合家賃を設定して、長く続けられるような構想を練っていった。これは、「資本主義を適切にゆるめる」ということだと思うんです。金融資本主義よりローカルエコノミーのほうが、調整弁次第でスピード感をゆるめることができる。
青木 地域福祉にもつながりそうな発想ですね。いま福祉の世界では、事業所が自分たちできちんと稼げるようにと言われ始めています。でも、そもそも福祉は競争の価値観と相性が悪いんですよ。
中村 まさにいま藤野では路線バスの廃止が問題になってますね。高齢者の足であり地域のインフラなのに、ビジネス視点で捉えると経済合理性がない。でも、公共の視点で考えれば大事なものです。そういうときに、ビジネスとして成立するいい落としどころはないのかな?と。起業家ゴコロをくすぐられるテーマです。
栗原 燃えるところですよね。テクノロジーを加えたり、モデル次第では上手くいきそうです。
青木 これからは公共的な課題に対して、ヒューマンスケールを持った起業家がちゃんと対処してくれることが必要なんじゃないでしょうか。いわゆる民営化といって丸投げされても、それを食い物にしている民間企業がやってきて日本全国に同じようなモノができていくだけ。肝心な社会課題にはコミットしていないことが多々あります。そうではなく、その土地に住んでいる人たちがビジネスとしてうまくやれたり、顔の見える人たちのためにお金を調達したり、継続してその場を運営できる体制ができたらいいですよね。
中村 そう思います。あと、地方については大きな資本を入れてネットワーク化しないほうがいいんじゃないかと思うことがあります。能登半島地震のとき、断水で命の危機にさらされた人がたくさんいましたよね。知り合いから聞いた話ですけど、能登ではかつて各集落には井戸水と浄化槽があって、それで十分生活できていたそうです。ところが、この十数年で上下水道を配管してネットワーク化し、今回の地震で分断されてしまったと。かつての井戸水と浄化槽のような自律分散システムだからこそ回避できるリスクがあって、なんでもかんでもネットワーク化すればいいわけではないと思うんです。そこにあるものをいかにして使うかが大切というか。
青木 ネットワーク化して巨大化することにも弊害があるので、適用しないほうがいい分野があるということですよね。
中村 ローカルには違うレイヤーで存在しているものがある。それが「混ぜるな危険」です。
栗原 よく考えれば、教育も江戸時代までは自律分散型でした。いまは文科省が学習指導要領をつくっているけど、もともとは藩校があって、そこから生まれた人材が日本を支えてきた歴史がある。それはローカルの面白い教育があったからこそだと思います。近代以降は中央集権化、効率化の時代でしたが、これからは自立分散にこそ未来があるんじゃないかな。
ローカルコミュニティで生きる実感を取り戻す

青木 ローカルではアートの感性が開かれるという話がありましたが、とはいえ田舎って忙しくないですか? 草の刈払いとかしょっちゅうやらなくちゃいけない。しかも田舎の忙しさってGDPでみたらマイナスです。
栗原 刈らないと生活が成り立たないからね(笑)。そして、自然って圧倒的な力を持ってるから、みんなで協働するしかない。
中村 「税金払ってるからやらなくていいじゃん!」っていう話ではないんですよね。草を刈ることで地域住民とのコミュニケーションも生まれる。一緒に何かをやるという儀礼をとおして、共同体としての結束が高まる。
青木 ぼくらは携帯にしてもゲーム機にしても、ポータブルになっていった時代を生きてきました。一家に一台から一人一台になっていき、消費活動が進めば進むほど、コミュニティが崩壊し個人化していった。しかも、どこかでそれが自由だと思い込んでいたけれど、結果的に孤立につながっていた。ところが、ローカルではなんでもかんでも個人ではなくコミュニティ単位で行う必要がある。だから、コミュニティがないと人間が生きられないことが、実感としてわかってくる。
中村 東京にいくと、みんなAirPodsでノイズキャンセリングしてるじゃないですか。パーソナルエリアがとにかく狭い。藤野ではノイズキャンセリングも必要ないし、開放的。コンビニの店員にも「どうも~」って言っちゃうくらいです。でも、東京のファミマであいさつしたら、「気持ち悪い人」になっちゃう(笑)。身体感覚が田舎モードになるんですよね。こういうところでビジネスをやろうとすると、つながりを作るためにビジネスを活用することになる。東京的なビジネスとは、構築の仕方が違うことができるようになるし、そこに面白さを感じています。
※AirPodsは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。