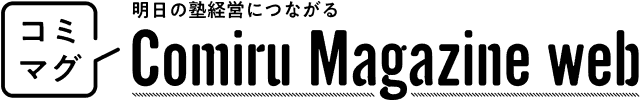塾・スクールを運営していると、どうしても避けられないのが保護者からのクレーム。問い合わせに近い内容もあれば、正当な要求とも取れるクレームも…。
塾・スクールは、クチコミが生徒集客を左右する世界。どんなクレームにも、適切な対処を心がけなければいけません。今回は、塾・スクールへのクレームについて、その原因や保護者の心理や、適切な対応方法について解説します。
塾・スクールへのクレームの原因は?保護者の心理とは
塾へのクレームは基本的に保護者からのものです。大切な我が子を、お金を払って塾・スクールに預けている以上、大なり小なりの不満を持つことはよくあることです。その場で「これはどうなっているのか」と直接訴えてくれるならまだ対処がしやすいのですが、小さな不満や不安が積もり積もって表面化したタイミングで、クレームではなく退塾の電話になっていることも多いでしょう。
ある学習塾で、クレームや退塾理由の分析を行ったところ、以下のことがわかりました。
入塾して半年間での退塾:塾の不手際が原因
入塾して半年〜1年での退塾:コミュニケーション不足
入塾して1年後以降の退塾:成績不振
すべての塾・スクールに当てはまることではありませんが、クレームを未然に防ぐためにも、自塾の退塾理由やクレーム内容を分析し、退塾やクレームが発生する前に対策を打つ必要があります。
クレームに繋がりやすい保護者の不満

一般的に、保護者の満足度が下がる理由は次の3つです。
- 成績が伸びていない
- サービスが金額に見合っていないと感じる
- コミュニケーション不足
こうした問題に対するクレームは、真摯に対応することで逆にファン化することが可能です。
クレームの原因① 成績が伸びていないこと
最も多いクレーム原因は、子どもの成績が伸びていないことです。保護者が塾・スクールに求めていることは「子どもの成績を上げること」であることは疑う余地もないことです。塾・スクールとしては、保護者の「成績が伸びていない」という判断基準がどのレベルなのかをある程度把握しておかなければなりません。
次の定期テストで成績が上がるかどうかを見ているのか、年度内に上がればいいのか、入試までに上がればいいのか、学校の平均より順位が上にいけばいいのか、など、保護者の価値観にもいろいろあります。
保護者との入塾面談時に、成績についての価値観や目指すゴールについて、保護者からきちんと引き出し、お互いに目線を合わせ、塾内で情報共有しなければなりません。
そのためにも、塾の成績管理ツールの一元化と情報共有は重要です。学校の定期テスト、通知表、模試、小テストなどの成績はデータで管理し、成績が下がった生徒を把握できるようにしておく必要があります。そうすれば、保護者からのクレームが来る前に対策を講じたり、クレームを受けたとしても、今後の対応をすぐに答えられることで、保護者の不安を少しでも取り除くことができます。
また、成績が上がらない原因や理由を生徒視点で把握することも重要です。授業中に変わった様子はないか、宿題忘れがないかなど、生徒の様子に気を配りましょう。
保護者の希望通りに成績が上がっていなくても、真摯な対応と今後の課題や見通しを伝えるだけでもクレームは激減します。それが保護者の安心感、満足度の向上に繋がるのです。
クレームの原因② サービスが金額に見合っていないと感じた時
価格とサービスのバランスは非常に大切です。保護者にとって、塾に通わせるのは投資と同じです。保護者は「成績が上がる対価」としてお金を払っています。
しかし現実的には、入塾してすぐに成績が上がり続けるわけではありません。「成績が上がる取り組みをこれだけしている」「成績上位者の特徴であるこのような学習習慣がついてきた」等、保護者に定期的に報告し、情報を共有していかなければなりません。
特に学習塾業界は、他のサービス業と違い、お金を出している人(保護者)とサービスを受ける人(生徒)が違うという、珍しい業界です。レストランであれば、お金を払うお客様においしい料理を提供すれば満足していただけます。しかし、学習塾は、どんなに生徒に手厚く対応したとしても、そのことが保護者に伝わっていなければ満足度が下がる業界なのです。
特に高単価となる個別指導形態の塾は、毎回の授業報告をすぐに保護者にお知らせするだけでなく、子どもの成長や変化を、具体的なエピソードを交えてきめ細かく報告することが重要です。
サービスの価値は、保護者の価値観ともつながっていますから、入塾時の保護者面談でしっかりヒアリングしておき、教室内で常に情報共有しておくことが欠かせないでしょう。
クレームの原因③ コミュニケーション不足
保護者とのコミュニケーション不足はクレームに直結します。保護者の立場で考えてみましょう。
- 塾でしっかりやっているか
- ちゃんと理解して進められているか
- 友達と騒いだり、遊んだりしていないか
など、不安はいつも持っているものです。保護者は塾・スクールでの我が子の様子は見えません。特に思春期の子は、「今日の塾はどうだった?」と聞いても、「べつに」「ふつう」とそっけない返事しか返ってこないものです。
対象年齢によっては、授業の様子を写真に撮って送るのも良いでしょう。少なくとも、その日の授業内容をまとめた指導報告書はその日のうちに送り、課題が残ったり、生徒の様子がいつもと違うなどの共有はきちんと行いましょう。
コミュニケーションは、質も大切ですが、量も同じくらい大事です。塾からのお知らせもとりこぼさないようにしてもらうのと同時に、保護者からも連絡しやすいツールを用意すること。コミュニケーションが密に取れれば、お互いの不満の芽が大きくなる前に対処することができるはずです。いちいち面倒だな…と思うかもしれませんが、結果、これが解決の近道だと思います。
参考:保護者からのクレームはなくせる!クレームにならないコミュニケーションのコツ
もしクレームを受けてしまったら?

塾・スクールへのクレームはいつくるか予想ができません。分かっていれば先手を打てますが、既に発生したクレームに対しては適切な対応をしなければなりません。
クレーム対応のポイントは次の3つです。
- 事実を客観的に確認し、塾・スクール側に落ち度がないか考える
- 問題があれば迅速かつ真摯に対応する
- 生徒や保護者とのコミュニケーションを改善する
他にもやるべき対応法はありますが、まずはこの3つをしっかりとやりきる方向を目指しましょう。
事実を客観的に確認し、塾・スクール側に落ち度がないか考える
まずは、クレームが寄せられた内容について客観的な事実を確認しましょう。保護者の声だけを聞くのでなく、該当する講師など関係者の話も聞いて総合的に確認することが重要です。塾・スクールに寄せられるクレームの中には理不尽なものもありますが、塾・スクール側に落ち度がある場合も少なくありません。まずは自分たちに落ち度がないかを考えましょう。
- どのレベルを目指して指導をしたか
- 成績向上のために何をしたか
- プランニングは明確で正確だったのか
- コミュニケーションは十分にできていたか
- 対応を放置していなかったか
- 質問への対応や補習は十分な内容だったか
- 生徒に対してどれだけの時間をかけて対応したか
- 不満の芽はどこまで把握できていたか
このように自塾の考えややり方を見つめ直すことで、保護者にどう対処するかを考えましょう。
問題があれば迅速かつ真摯に対応する
まずはクレームに対して対応できることとできないことを明確にし、保護者にはっきりと伝えましょう。できない要求に対してははっきりと伝え、できる範囲の対応を明確にし、要求されそうな要素については事前に予測し返答します。クレームに対しては「鉄は熱いうちに打て」が鉄則です。
さらに、一連の対応と改善策の具体的な内容は、スタッフ全員に共有し、必ず実行するようにします。クレームに対して真摯に向き合い、対応することが、結果的にファン化を促進してよい顧客となることもあります。
生徒・保護者とのコミュニケーションを頻繁にとる
クレームへの対応で最も大切なのがコミュニケーションの強化です。コミュニケーションをしっかり行うことで、不満から満足度改善に繋げましょう。
保護者が気にしていることはこまめにフィードバックし、メールやメッセージの未既読を確認しながらコミュニケーションを取り続けましょう。
参考:退塾防止や弟妹通学率の向上に! 保護者コミュニケーションの重要性とその手法
塾・スクールへのクレームを回避するために
クレームはどんなに気をつけていても起こり得るものです。クレームが発生する度に、その原因を分析し、二度と同じことが起こらないような対策をその都度講じておけば、クレームの数を大幅に減らせます。
成績を上げることもコミュニケーションを深めていくことも、両方大事なこと。そこに時間をかけられるよう、業務の効率化はどんどん進めていきましょう。Comiruのような塾・スクール専用のシステムは、その一助になります。
そもそもコミュニケーションを電話・メールに頼っていませんか?指導報告書を手書きで作成して子ども経由で渡していませんか?
システムでお互い便利にできること、対面で直接伝えることなど、コミュニケーションをうまく取り、保護者の不満の芽を見つけやすくすること、その芽をすぐに摘めるようにすることを心がければ、例えクレームが来ても怖くはありません。
塾・スクールへのクレーム対応まとめ
クレーム対応は、塾・スクールにとって「トラブル処理」ではなく、「信頼を積み重ねるチャンス」でもあります。
多くのクレームの背景には「成績が上がらない」「サービスが金額に見合わない」「コミュニケーションが不足している」といった不満があります。こうした原因を正しく理解し、日頃から目標や価値観をすり合わせ、情報共有や報告を丁寧に行うことが、クレームの芽を小さいうちに摘み取る第一歩です。
そして、もしクレームが起きたときは、迅速で誠実な対応を徹底し、今後の改善策までしっかり示すことで、保護者との信頼関係をより強固なものにすることができるでしょう。