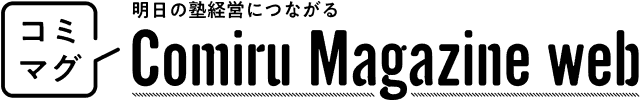監修いただいた先生
塾・スクールは初期投資が少なく、開業しやすい業種の1つです。その分、多くの塾が乱立しているため、塾経営に失敗するケースも多く見られます。東京商工リサーチの調べによると、少子化や受験の多様化、個別指導、オンライン授業の台頭などで、学習塾の経営は難しさが増し、学習塾の約3割が赤字、約20社の大手塾が市場の66.2%をおさえているのが現状のようです。
参考:TSRデータインサイト「学習塾の約3割が赤字 約20社の大手塾が市場の66.2%をおさえる」,(東京商工リサーチ)
厳しい業界の中でも、生徒・保護者の信頼を集め、地域に根付いて健闘している塾・スクールもあります。今回は、塾・スクール経営の失敗するパターンを分析し、失敗しない対処法を考えます。
塾・スクールは開業しやすい一方で廃業も多い
塾・スクールが他業種と比べて開業がしやすいということは、参入障壁が低いということです。小さな塾・スクール、なら教室と教材、机、椅子などの備品があればすぐにスタートできます。しかし、開業は簡単でも、塾経営が成功するとは限りません。東京商工リサーチの調査によると、2024年の学習塾の倒産件数は53件で、2000年以降で過去最多となっています。倒産する塾には大手塾やFCの強豪塾も含まれており、とても競争が激しい業界だと言えるでしょう。
この中で勝ち抜いていくには差別化戦略による事業展開が必須です。塾・スクール経営者が陥りがちな失敗パターンから、成功の秘訣を探ります。
塾経営の失敗①大手塾と同じ戦略をとる
大手塾の戦略は、基本的には資本力のある強者の戦略です。売上の5〜10%とも言われる巨額な広告宣伝費を投下し、認知度と生徒数に比例する合格実績で勝負を仕掛けます。高い知名度と集客力を持つ大手塾と同じことをしても、小規模塾では対抗できません。
大手塾に対しては、自塾にしか提供できない価値で、徹底した差別化戦略を図り、小さな市場でリーダーになることです。特定の小さな市場で特定のニーズに合ったサービスを提供することで、顧客の支持を得られる可能性は十分にあります。
例えば、小規模塾ならではの生徒一人ひとりに向き合う指導や、特定の学校に特化した指導など、、生徒数の多い大手塾ではなかなか対応できないところを狙うという手もあります。
差別化の例:
- ◯◯中学校の進度に合わせた指導
- △△高校を目指す
- 部活と両立しやすい
- 家庭学習の進捗もフォロー
- 講師は全員◎◎大学卒業生(または現役生)
塾経営の失敗②立地の悪さで集客が難航
塾経営の失敗には「立地の悪さ」が原因となることもあります。立地が悪いと、どれだけ素晴らしい授業でも生徒を集めるうえで不利になります。
立地が原因で思うように集客が伸びないと考えられる場合は、送迎時の駐車スペースや駐輪場を用意したり、立地が悪くても通わせたくなる塾運営に舵を切り直すのもよいかもしれません。他塾にはない魅力的な授業・講師、丁寧な保護者コミュニケーション、振替など手続きのしやすさなど、とれる戦略はたくさんあるでしょう。
塾経営の失敗③価格競争で対抗する
大手をはじめ、他塾と生徒の取り合いになると巻き込まれやすいのが低価格戦略です。体力のある事業規模であれば耐えられますが、小さな塾では安易に乗ってしまうと命取りになります。
まず相手が大手塾の場合。大手塾は一つの教室で赤字が出ても、収益率の高い教室で補填ができるため、企業全体で収益のバランスを取ることができます。このようなリスク分散は小規模塾では難しいでしょう。
価格で勝負するのではなく、自塾の強みを最大限に活かして、価格ではなく質の高いサービスで戦うべきです。仮に月謝が5000円高くても、「面倒見が良い」「親身に相談に乗ってくれる」「授業後に気軽に質問しやすい」など、大手塾が苦手な小回りの効くサービスが提供できれば、生徒を集めることは可能です。
塾経営の失敗④ICT活用やオンライン対応ができない
塾業界は他業界に比べてDX(デジタルトランスフォーメーション)化が遅れていると言われていましたが、コロナの影響や生成AIの台頭もあり、IT化が不可欠な時代になりました。
大手塾はもともとシステム導入が進んでいましたが、今では小規模塾も業務系、決済系のシステムを導入するところが増えています。
そんな中で、いまだに「紙で手書きの指導報告書」「手紙でのお知らせ配布」「電話連絡」「請求書・口座振替伝票郵送」など、アナログな運用をしているのは少し危険です。アナログ運用は業務効率が悪いため、生徒・保護者対応が疎かになりやすく、教務に支障が出ることもあります。
塾業務のデジタル化もさることながら、オンライン授業やオンライン保護者会、SNSを活用したマーケティング、集客など、今どきの生徒・保護者の生活スタイルに合わせたサービスの提供やICT活用を積極的に始めましょう。
特に、オンラインコースを設置することで、塾の周辺以外からも集客が可能になります。高校進学のタイミングで距離的に通塾が難しくなって退塾した生徒を、オンラインで呼び戻した例もあります。
塾経営の失敗⑤集客戦略が不十分、時代に合っていない
チラシのばら撒きや門配での集客はそろそろ時代遅れかもしれません。小規模塾だからこそ、重要なのはペルソナを意識したターゲティング戦略です。どのあたり(地域やレベルなど)の学校に通うどんな生徒を狙うのか、保護者はどんな人たちか、具体的にイメージしながら集客戦略を立てていきましょう。それによって、SNSを活用するのか、口コミ・紹介キャンペーンを実施するのかなど、打ち手が変わってきます。
参考記事
効果的な塾の集客方法とは?さまざまな媒体を活用したマーケティング
まとめ
簡単に開業できても、継続させるのが難しい塾・スクール。大手塾やFCの塾も倒産する時代で、とても競争が激しい業界だと言えます。
この中で勝ち抜いていくには差別化戦略による事業展開が必須です。今回は、塾・スクール経営者が陥りがちな失敗パターンから、成功の秘訣を探りました。
塾経営の失敗①大手塾と同じ戦略をとる
→大手塾に対しては、自塾にしか提供できない価値で、徹底した差別化戦略を図り、小さな市場でリーダーになることを目指す。
塾経営の失敗②立地の悪さで集客が難航
→立地が悪くても、送迎時の駐車スペースや駐輪場を用意したり、提供価値を上げることで塾の魅力に繋げる。
塾経営の失敗③価格競争で対抗する
→価格競争では大手塾に勝てない。価格ではなく価値で勝負する。
塾経営の失敗④ICT活用やオンライン対応ができない
→今どきの生徒・保護者の生活スタイルに合わせたサービスの提供やICT活用を進める。
塾経営の失敗⑤集客戦略が不十分、時代に合っていない
→ペルソナを意識したターゲティング戦略をたて、ターゲットに有効な集客手段を選ぶ。