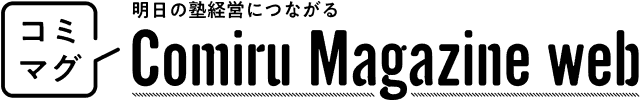塾で生徒に向き合う中で、思わず厳しい言葉を使ってしまうことはありませんか?
講師としては「成長してほしい」「気づいてほしい」という思いからの言葉でも、生徒にとってはパワハラのように感じてしまうこともあります。
この記事では、塾でありがちな声かけ例をもとに、“叱る”と“怒る”の違いや、言葉が指導になるかパワハラになるかの境界線を解説します。
講師から生徒へのパワハラとは
講師が生徒に指導する場面で起こりがちなハラスメントがパワハラです。
- 「こんなこともわからないのか!」
- 「さっき説明したよね?」
- 「前と同じ問題なのになんでわからないの」
など、言葉や態度に出てしまい、それを生徒が不快に感じればパワハラは成立します。当然、大きな音を立てて机を叩いたりする行為もパワハラになり得ます。
「こんな簡単な問題なのにどうして解けないの?」そんな一方的な感想を、うっかり生徒にぶつけたことはありませんか?パワハラが起こってしまったら、後が非常に大変です。絶対に起こらないように、チームで取り組む必要があります。
「怒る」と「叱る」は違う
何がパワハラになるかを考える前に、まず大前提として、「怒る」と「叱る」は別物であることを押さえておきましょう。
怒る:自分の感情をぶつける行為。教育的な意図がない。
叱る:生徒の成長を目的とした、教育的な意図をもった声かけ。
塾講師として生徒と信頼関係を築いたうえで、「叱る」ことは必要です。ときに厳しい言葉があっても、関係性と意図が伴えば“成長のきっかけ”となる指導になる。逆に、感情のままに言葉をぶつけてしまえば、パワハラになりかねません。
指導とパワハラ、境界線はどこにある?
同じ言葉でも、「指導」と受け取られるか「パワハラ」と感じられるかは、その背景にある要素で大きく変わります。
以下の4つは、指導とパワハラを分ける主な分岐点です。それぞれについて具体的に見ていきましょう。
① 目的が「生徒の成長」にあるか?
指導とは、本来「生徒の学力や姿勢を良い方向に導く」ことが目的です。
一方、怒りや不満のはけ口として言葉を使ってしまうと、それは指導ではなく“感情の発散”となり、パワハラと捉えられてしまいます。
✅【指導】「この問題を理解すれば次に進めるよ。一緒に確認しよう」
❌【パワハラ】「何でこんなことも分からないの?」(目的が伝わらない)
② 信頼関係のうえに成り立っているか?
厳しい言葉も、日頃の関係性がしっかりしていれば「先生は本気で向き合ってくれている」と生徒に伝わります。
しかし、関係性が築けていない状態で強い言葉を投げると、ただの威圧や否定として伝わってしまうのです。
✅【信頼あり】「厳しいけど、この先生の言うことなら頑張ろうと思える」
❌【信頼なし】「また怒られた…嫌われてるのかも」
③ 感情的になっていないか?
その言葉は冷静に、指導として選び取ったものですか? それとも、イライラや焦りに任せて出たものですか?
感情的な言動は、どんなに正論でも相手を萎縮させ、意図が伝わらなくなってしまいます。
✅【冷静に】「これまでの復習が必要そうだね。もう一回整理しよう」
❌【感情的に】「なんで何度も言ってるのにできないんだ!」
④ 相手の“人格”ではなく、“行動・事実”を指摘しているか?
「だらしない」「君には無理」といった言葉は、生徒の人格を否定する表現です。
これに対して、「今日は宿題ができていなかったね」「集中が続いていないようだったね」など、“行動”に焦点を当てたフィードバックであれば、生徒は反省し、改善しようとするきっかけになります。
✅【行動への指摘】「宿題ができていなかったね。いつまでにやる?」
❌【人格への否定】「君ってやる気ないよね」
この4つを意識するだけで、同じ内容でも伝わり方は大きく変わります。特に塾のように、子どもたちの成長を支援する場では、“伝えること”以上に“どう伝わるか”が重要です。
パワハラになりそうな言葉10選と、注意点・望ましい言い換え例
塾でよく使われがちな10のフレーズを取り上げ、どのように伝え直せば「叱る」になるのか、解説します。
①「なんでこんな簡単な問題も解けないの?」
【注意点】
“できないこと=悪いこと”と責める印象が強く、萎縮や自己否定につながります。
【言い換え例】
「この問題、どこでつまずいたかな?一緒に考えよう」
②「お前ら、集中しろよ!」
【注意点】
集団に怒鳴るような声かけは、威圧感があり恐怖や反発を生むことも。
【言い換え例】
「少し疲れてきたかな?あと10分、集中してみよう!」
③「宿題やってこないなら来なくていいよ」「やる気がないなら帰っていいよ」
【注意点】
突き放す態度がパワハラと受け取られ、関係が悪化します。拒絶されたように感じる生徒もおり、モチベーション低下や不登校につながる可能性も。
【補足】
ただし、塾によっては“本気の子だけを伸ばす”という方針で、戦略的にこのような言葉を使うこともあります。その場合でも、生徒との信頼関係と教育的意図が伝わっていることが前提です。
【言い換え例】
「次は宿題、期待してるよ。一緒に頑張ろうね」
④「こんな成績じゃ将来どうするの?」
【注意点】
未来への不安を煽る言い方は、生徒に“絶望”を感じさせることがあります。
【言い換え例】
「このままだと少し心配。でも今から頑張ればきっと変わるよ」
⑤「何回言えばわかるんだ!」「前にも言ったよね?」
【注意点】
過去の失敗を責められているように感じやすく、反省ではなく自信喪失につながる可能性があります。
【言い換え例】
「ここはすごく重要だから、もう一度確認するね。次回までに覚えておこうね」「繰り返すと身につくから、もう一回確認してみよう」
⑥「他の子はできてるのに、どうしてできないの?」「君みたいな子は初めてだよ」
【注意点】
比較はやる気につながるどころか、生徒の自己肯定感を傷つけてしまうことも。言い方によっては、“厄介な子”とレッテルを貼られたと感じさせてしまいます。
【言い換え例】
「人によって得意・不得意があるから大丈夫だよ」「違う解き方でやってみよう」
⑦「ちゃんとやれって言ったよね?」
【注意点】
責めるトーンになりやすく、言われた内容より“怒られた”印象が残ってしまいます。
【言い換え例】
「どうすればもっとスムーズにできるか、一緒に考えよう」
⑧「君のせいで授業が遅れた」
【注意点】
責任を一方的に押しつける形になり、生徒を追い詰める表現です。
【言い換え例】
「もう少しテンポよく進めよう。みんなのためにも協力してほしいな」
⑨「こんな成績でよく平気だね」
【注意点】
皮肉ともとれる言い方で、自尊心を深く傷つけます。
【言い換え例】
「成績、ちょっと心配だね。次のテストで一緒に巻き返そう」
⑩「他の塾ならもっと厳しいよ」
【注意点】
脅しや否定として受け止められやすく、“ここが合わないなら出ていけ”というニュアンスに取られる可能性も。
【言い換え例】
「この塾でもしっかり力をつけられるよう、一緒にがんばろうね」
大切なのは「意図」と「信頼関係」
厳しい言葉そのものが悪いわけではありません。信頼関係のうえで、教育的な意図がしっかり伝わるなら、時には強い言葉も“指導”になります。
しかし、感情的に投げつけられた言葉は、生徒にとってはただの“怒り”や“否定”でしかなくなってしまいます。
叱る=意図と配慮ある言葉で成長を促すこと
怒る=感情をぶつける行為
この違いを意識しながら、日々の指導に臨んでみてください。
パワハラの判断はケースバイケースであり、グレーゾーンが非常に多いと思います。だからこそ、いろいろなケースを想定し、対策しておくことが必要です。教室長、講師、スタッフ全員でロールプレイを実践してみましょう。「NG例」と「改善例」を実際に演じ、違いを体感してもらうことで、パワハラへの意識が高まり、防止につながります。