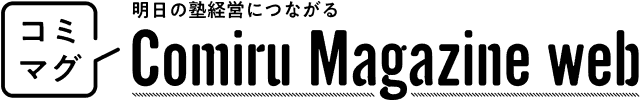監修いただいた先生
コロナ禍を経て、教育業界ではオンライン授業が多く取り入れられるようになりました。総務省の「経済構造実態調査」によると、インターネットを活用した指導方法を取り入れている学習塾の事業所数は、
2019年 : 14,709件(全事業所数の27.9%)
2020年 : 22,291件(全事業所数の42.8%)
と、急増しています。2020年の時点で、既存事業所数のおよそ半数がインターネットを使ったオンライン指導を取り入れています。
Z世代の生徒とその保護者の価値観は、コスパやタイパを求める風潮など、昔と大きく変わってきています。そんな時代において、インターネットをフル活用した塾経営は、今後の発展の鍵を握る可能性を秘めていると言えるでしょう。そこで今回は、オンライン塾の運営についてご紹介します。
一般塾のオンライン授業とオンライン専門塾
オンライン塾には、対面授業を行っている塾がサービスの一部として提供するオンライン塾と、インターネット上でのみ授業を提供するオンライン専門塾があります。どちらにもメリット、デメリットがあるため、塾の理念や今後の戦略、指導方針に合うかどうか、しっかり見極めなければいけません。
一般塾のオンライン授業
個人授業でも集団授業でも、オンライン授業を取り入れている学習塾は増えていると思います。コロナ禍のように、通塾ができない状況でもいつもの先生の授業を受けられたり、人気講師の授業を教室を超えて受けられたりするなど、そのメリットは広く認知されているでしょう。授業ノウハウを活かせる分、導入ハードルも低く、インフラさえ揃えばすぐに始められるでしょう。
簡単に始められるとは言え、オンライン授業ならではの課題もあります。その一つが、「集中力やモチベーションの維持」です。
オンライン授業では、PC画面という制約のある空間での生徒指導になります。生徒はPCやタブレットの画面を長時間見続けなければならず、飽きさせない工夫や集中力を維持する空気づくりなど、対面授業とは違うノウハウが新たに必要になります。
先生からすれば、テキストを見ている様子や生徒がノートをとっている手元が見えず、画面の生徒の表情から理解度や授業態度を推測するしかありません。従って、今ある授業を単にインターネットで配信する、というだけでは失敗する可能性が高いでしょう。
例えば、
- 目的を対面授業の反復学習とし、家庭学習を強化するツールとする
- 通塾できない、または欠席生徒のために授業を中継する
- オンライン授業で学習し、対面授業では演習中心にする
など、対面授業とオンライン授業のすみ分けを戦略的にしっかり考えないといけません。
オンライン専門塾
最近増えてきたのがオンライン専門塾です。科目指導の専門知識はもちろん、授業をしながら生徒の心理状態を感じ取る能力、メリハリのある授業展開、生徒が集中力を失った時を感じ取り、適度にユーモアや叱咤激励をして空気を引き締める能力などの経験値が必要になります。
また、物件や講師の確保が不要で初期費用があまりかからないため参入障壁が低く、地域関係なくどこでも開業することができます。競合も多いということは、コンセプトや強みの差別化とターゲティングがとても重要です。
例えば、エヌラボスタディの例をご紹介します。エヌラボスタディは地域に根付いた小さな個人塾で、対面授業を行なってきました。塾長が地方に住み替えをしたため、「その場所」では運営できなくなり、オンライン専門塾として再スタートしました。それから数年経ち、今では「国語専門のオンライン塾」として、全国各地、最近ではサウジアラビアの生徒まで在籍しています。ずばり、差別化ポイントは「国語専門」です。
数あるオンライン塾とどう勝負するか、エリアを絞ってターゲティングする一般塾よりも尖ったコンセプト、エッジの効いた訴求が必要なのです。
オンラインで指導するメリット
対面授業とオンライン授業のハイブリッド型、オンライン専門型とも共通しているメリットは、顧客層の拡大を狙えることにあります。距離的に通塾困難で通えなかった生徒や、海外に住む日本人も対象になるでしょう。最近激増している不登校の子どもも対象になってきます。
講師の人数を多く確保できなくても、塾経営に大きく影響しないことも大きなメリットと言えるでしょう。
今では家庭のインターネット環境も万全であることがほとんどで、お互いに手軽に始められる状況にあります。
オンライン授業・オンライン専門塾の始め方
条件さえ整えばすぐにでも始められる分、「とりあえず」でスタートするのは非常に危険です。一度ネガティブな印象が付けば、その情報はすぐに拡散されてしまいます。
オンライン指導で準備するもの
オンライン授業に最低限必要なものは「映像が映せるPC」と「しっかりしたネット環境」です。ネット環境は30Mbpsはあると良いでしょう。生徒や講師が増えたら他にも便利なツールを導入すればいいと思いますが、まずはこの2つで始められます。
だからこそ、きちんと集客するための努力をしなくてはいけません。
ホームページはきっちり作り込む
まずは塾の入り口、ホームページをきちんと作り込むことから始めましょう。特にオンライン専門塾はここが要になります。おそらく、複数の同業他社を比較して目が肥えています。「この塾の強みは何か」「自分(自分の子ども)に合っているか」「講師の質はどうか」「成績は上がるのか」など、ターゲットが気になるポイントについてしっかり訴求しましょう。
ターゲットに訴求するということは、ペルソナ設計ができていなければなりません。どんな生徒、保護者にどんな価値を提供したいのか。ホームページのデザインもペルソナを意識するとより良いものになります。
SEO対策も重要です。せっかくホームページを作っても、特色が出せていないと検索時に上位表示されないため、集客力は格段に落ちてしまいます。
参考記事:あなたの塾のサイトは大丈夫? WEBサイトの構築・運用において重要な視点とは
最初は少しお金をかけてでも、きちんとしてホームページを準備することをおすすめします。
オプションとしてのオンライン授業
対面授業がメインの塾がオンライン授業を始める場合、それを補助的なツールとして活用するなら既存ホームページからの導線を作るだけでも構わないと思います。しかし、今後はオンライン授業のみの生徒を受け入れる、つまりオンライン授業をフックに集客を考えるなら、専用の新しいページを立ち上げるべきでしょう。
最近では、科目によって映像授業を取り入れる学習塾も増えてきました。これも新しいターゲットを集客できるすばらしいツールだと思います。
映像授業を始めるならComiruAirが手軽でおすすめです。実際の導入事例や、どんな使い方が良さそうか、塾の運用方針に合わせた提案など、お気軽にご相談ください。
まとめ
今回は一般塾のオンライン授業とオンライン専門塾についてご紹介しました。対面授業がメインの塾がオンライン授業を取り入れる場合、それらのすみ分けを戦略的に考えておきましょう。
例えば以下のようなポイントが考えられます。
- 目的を対面授業の反復学習とし、家庭学習を強化するツールとする
- 通塾できない、または欠席生徒のために授業を中継する
- オンライン授業で学習し、対面授業では演習中心にする
オンライン専門塾の場合、科目指導の専門知識はもちろん、授業をしながら生徒の心理状態を感じ取る能力、メリハリのある授業展開など、生徒を飽きさせない指導についての経験値が必要になります。競合も多いため、コンセプトや強みの差別化とターゲティングがとても重要になります。
どちらの場合も、「映像が映せるPC」と「しっかりしたネット環境」さえあればすぐにでも始められる分、「とりあえず」でスタートするのは非常に危険です。特にオンライン専門塾はホームページの作り込みに注力しましょう。誰にどんな価値を提供したいのか、ターゲットのペルソナを意識しながら、SEO対策にも力を入れましょう。
次回は、オンラインならではの集客についてお伝えします。