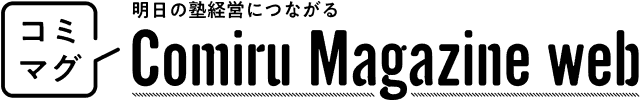監修いただいた先生
前編では、クチコミのきっかけをつくるアナログ施策をご紹介しました。今回は、保護者や生徒が「ちょっと気になる」と思ったときに調べるデジタル空間での工夫をご紹介します。
紹介は、信頼できる相手から「いいよ」と言われて終わりではありません。そのあと、紹介された側がネットで情報を検索する──そのときに「やっぱりよさそう」と思ってもらえることが大切です。
つまり、紹介→検索→納得というステップを想定した見える化が、紹介を確かな入塾につなげるポイントになります。
④Googleビジネスプロフィールで「見つかる・伝わる」
Googleビジネスプロフィールを活用し、塾の情報を充実させることで、保護者や生徒からのクチコミを集めやすくなります。それと同時に、オンラインでの信頼性と検索時の認知度を高めることができます。
基本情報を正確に登録する
まずは、Googleビジネスプロフィールに、塾の営業時間、住所、電話番号、公式ウェブサイトへのリンクを正確に登録しましょう。また、プロフィールには、教室の写真(授業風景、笑顔の生徒、掲示板など)、最新の合格実績、無料体験授業の案内を追加しましょう。説明文には「地域密着で成績アップをサポート!」などといったキーワードを盛り込むとよいでしょう。
Googleビジネスプロフィールへのクチコミの収集
保護者面談や授業後に、LINEやメール、Comiruのようなメッセージツールを使って「Googleのクチコミ投稿にご協力ください」と依頼をします。Googleビジネスプロフィールのクチコミ入力フォームのリンクを案内するとよいでしょう。
協力者には感謝として塾オリジナルグッズ(例: ロゴ入りクリアファイル)をプレゼントなどの特典を。依頼文には「具体的なエピソードをいただけると嬉しいです!」と記載し、例文を添えておくと親切です。
例文
- 入塾時には30点台だった数学が、今では平均点プラス10点は取れるようになった。
- 勉強嫌いで30分も机に向かわなかった子(小5)が、気づけば2時間は学習している。
- 無理だと思っていた◯◯高校に合格、第二志望も合格。併願プランも親身に相談に乗ってくれた。
Googleビジネスプロフィールへのクチコミへの対応
意外と運用がわからないのがクチコミの返信。基本的には、新しいクチコミが投稿されたら、24時間以内に返信するのがよいとされます。その際、ある程度は定型文でもかまいませんが、毎回同じコメントは冷たい印象が残ります。否定的なクチコミには、丁寧に謝罪し、改善策を提示できるとよいでしょう。
例文
- 「〇〇様、温かいお言葉ありがとうございます!お子さまの成績アップにこれからも全力でサポートします。」
- 「ご不便をおかけし申し訳ありません。ご意見を参考に、授業スケジュールを調整します」)。
明らかな誹謗中傷コメントはGoogle社へ削除依頼をしましょう。即時対応ではないかもしれませんが、放っておくのはよくありません。また、事実と異なるコメントについては、「事実とは異なります」と正直に回答し、正しい情報を伝えるとよいと思います。
投稿機能を活用しよう
Googleビジネスプロフィールの「投稿」機能で、月2回を目安に、期間講習などのイベント情報や成功ストーリーを発信しましょう。どうしてもコンテンツがないと悩んだ場合は「友人紹介キャンペーン」でも構いません。投稿には「まずは体験授業へ!」と気軽なアクションを促す一文を入れ、ウェブサイトの予約ページにリンクさせましょう。
Google上で見られる評価もチェック
クチコミ数は信頼性の指標となり得ます。10件以上の高評価(星4以上)があれば、検索上位に表示されやすくなるなど、Google側のルールもあるようです。定期的にプロフィールを更新し、最新情報を保つように心がけましょう。
Googleでの検索時に塾の信頼性が可視化されていると、「評判の良い塾」と認識されます。クチコミをたくさん収集するのは時間も手間もかかりますが、クチコミが増えることで、既存の保護者や生徒も「自分も投稿しよう」と促され、紹介の好循環が生まれるでしょう。
⑤SNSやブログで「ストーリー」を伝える
クチコミが生まれやすいのは、合格実績などの数字よりも、生徒や卒業生のリアルなストーリーです。「合格体験記」や「成績アップ体験記」などうまくコンテンツ化しましょう。デジタルにまとめ、SNSなどで拡散しましょう
どんなストーリーがクチコミを生みやすいのか
生徒の合格・成績アップ体験記を5~10ページのデジタルブックレット(PDF形式)にまとめます。各ストーリーは300~500字程度で、生徒の声(例「数学が苦手だったけど、先生の指導で30点アップ!」)、保護者のコメント(例「子どもの自信がついた!」)、講師の補足を掲載します。
塾のロゴや教室の写真も使用しながら、全体的にカラフルで見やすく構成します。タイトルは「〇〇塾で夢を叶えた仲間たち!」など、最後に体験授業のQRコードを掲載しましょう。
保護者向けなのか、生徒向けなのかで仕立ては変わります。生徒向けなら文字数を少なめにし、図表やイラストを加えるなどの工夫をしましょう。保護者向けなら具体的な数字で実績をリアルに伝えましょう。
例
「◯◯中学3年・A君の物語:数学40点→85点!」
「△△高校3年・Bさんの合格記:偏差値50から偏差値64の〇〇大学へ!」
体験記の集め方と編集方法
体験記を作成するためには生徒の協力が不可欠です。学期末や受験後に生徒・保護者に体験記を募集するのをルーティン化しましょう。その際、回答しやすいように、Comiruのアンケート機能のようなフォームを活用するとよいでしょう。Comiruなら定型文も活用でき、運用の手間も省けます。
質問例(回答内容で個人が特定されることはありません。必要に応じて、事実を変えずに情報を伏せたり編集することがあります。)
- 塾に入る前と入ったあとの成績の変化を教科ごとに教えてください(1教科でも構いません)。
- 塾で印象に残ったこと、先生に言われて心に残ったことを教えてください。
- 志望校を決定するときのエピソードを教えてください。
- 受験にあたって、志望校を目指した時の成績、中間成績、直前の成績など、具体的なエピソードを教えてください。
- 成績アップにつながった学習法(授業後の見直しなど)、家庭学習のコツなどあれば教えてください。
例文
入塾時は英語の成績が3、定期テストで平均点に届かないくらいだったのが、6ヶ月後に70点台を取れるように。成績は4か5が平常に!」
参考になる例文を紹介しておきましょう。例文には具体的な数字を盛り込み、体験記にあるとよい情報をうまく引き出しましょう。最後に、体験談への掲載許可を得て、匿名またはイニシャルで掲載します。
PDF化した体験記をSNSなどを活用して配信しましょう。LINE公式アカウントがあれば、「リッチメッセージ」機能を使い、表紙画像と「体験授業申し込み」ボタンを目立たせます。シェア時にハッシュタグ(#〇〇塾成功物語など)を推奨し、SNSでの拡散も促進しましょう。
編集はプロのライターまたは塾スタッフが担当しましょう。5~8件の体験記を1冊にまとめたデジタルブックレットを、年2回発行できるとよさそうです。保護者面談でも案内ができ、「うちの子もここに載るかしら……」と期待してくれるかもしれませんね。
デジタルブックレットにも体験授業への導線を忘れずに
デジタルブックレットの各ページに「あなたもA君のようになれる!無料体験授業はこちら」などと、QRコードを記載しましょう。QRコードは専用ランディングページ(塾のウェブサイトの申し込みフォームなど)にリンクします。
ブックレットをダウンロードまたはシェアした非塾生が体験授業に申し込むと、紹介者、申し込んだ生徒ともに特典を提供します。入会特典としてよくあるのが「入会金割引、または無料」というものです。
⑥紹介が自然に起こる「仕組み」をつくるーーComiru活用例
最後は、紹介の声を取りこぼさない仕組み化の工夫です。
たとえば、Comiruを使っている教室では、定期的に紹介カードを配信する機能や、保護者へのメッセージに紹介制度を組み込むことで、紹介数が自然と伸びています。
【メッセージ例】
新年度が始まりましたね!「うちの子、〇〇塾で楽しく通っているよ」と感じたら、ぜひお知り合いにも教えていただけたら嬉しいです。 ご紹介特典もご用意しています。詳細はこちら▶https://...
また、紹介によって入塾した生徒を記録・分析することで、「どの保護者がどんなきっかけで紹介してくれたのか」も把握でき、紹介後のフォローにも役立ちます。
Comiruには、紹介が自然に起こる仕組みが揃っています。保護者の声を収集・編集しやすいComiruの「お知らせ機能」「アンケート機能」、生徒の授業態度や成績などを通じてコミュニケーションが生まれやすい「指導報告書」など、塾専用システムならではの便利な機能が盛りだくさんです。
後編のまとめ
紹介は「お願い」ではなく、「伝えたくなる仕組みづくり」。 その鍵となるのが、リアルとデジタルの両輪です。
- アナログの接点で“想い”が伝わり、
- デジタルの見える化で“信頼”が深まり、
- そして、紹介したくなる“仕組み”が用意されている。
そんな状態をつくっていけると、紹介は特別な施策ではなく、日常的に生まれる自然な流れになります。ぜひ、教室に合った方法から一歩ずつ試してみてください!
- 「LINE」は、LINEヤフー株式会社の商標または登録商標です。
- 「Google」、「Chrome」、「Android」、「Android」ロゴ、「YouTube」、「YouTube」ロゴ、「Gmail」、「Google Authenticator」、「Google Authenticator」ロゴ、「Google Play」、「Google Play」ロゴ、は、Google LLC. の商標または登録商標です。
- 「QRコード」は、株式会社デンソーウェーブの商標または登録商標です。